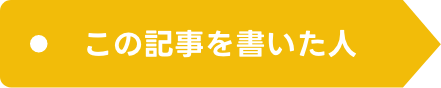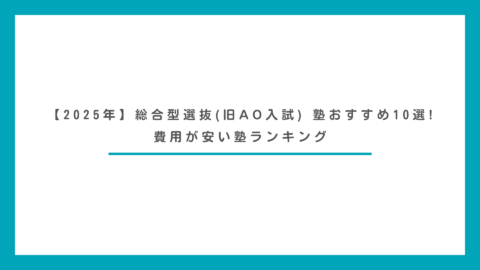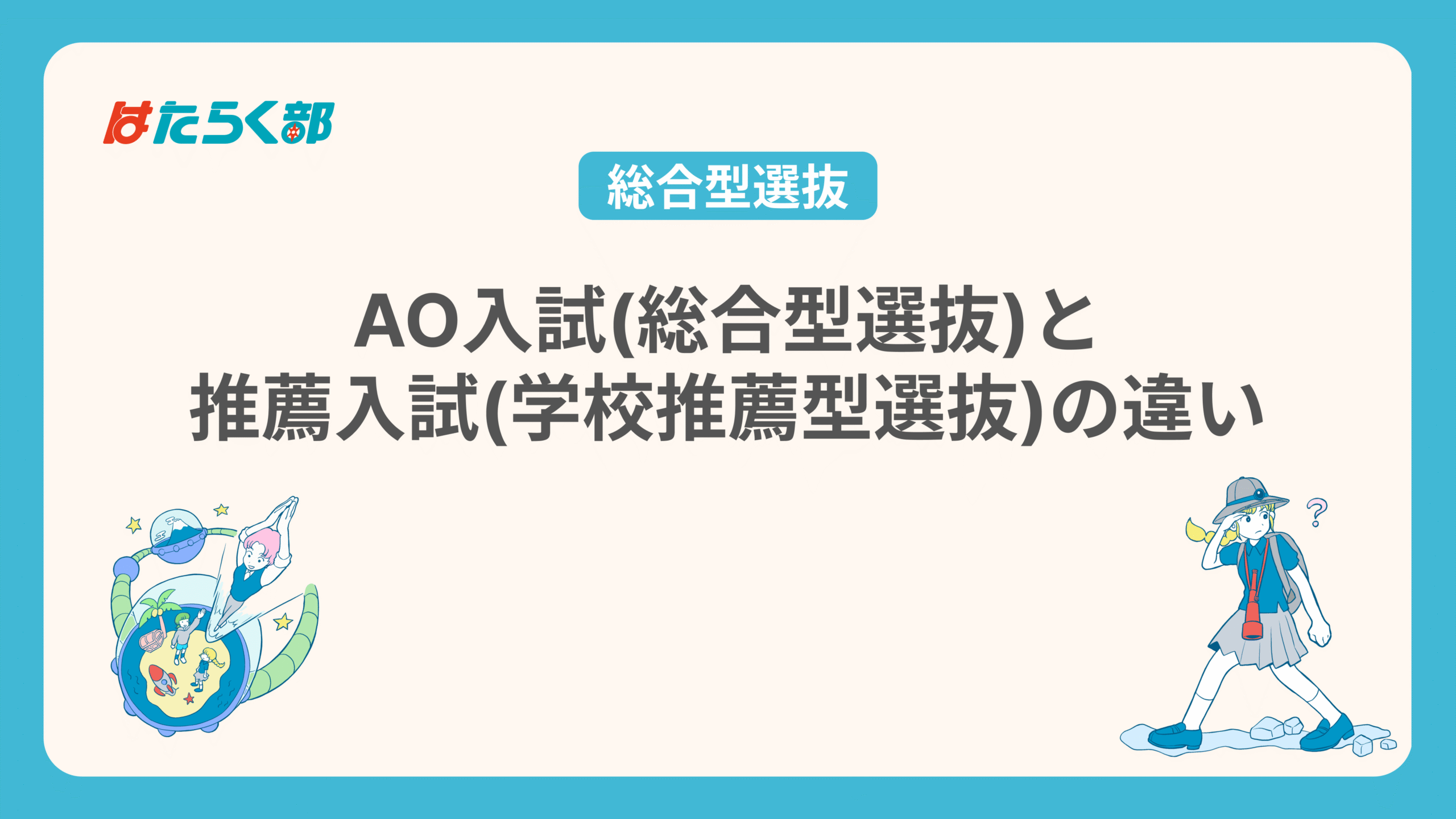ブログBlog
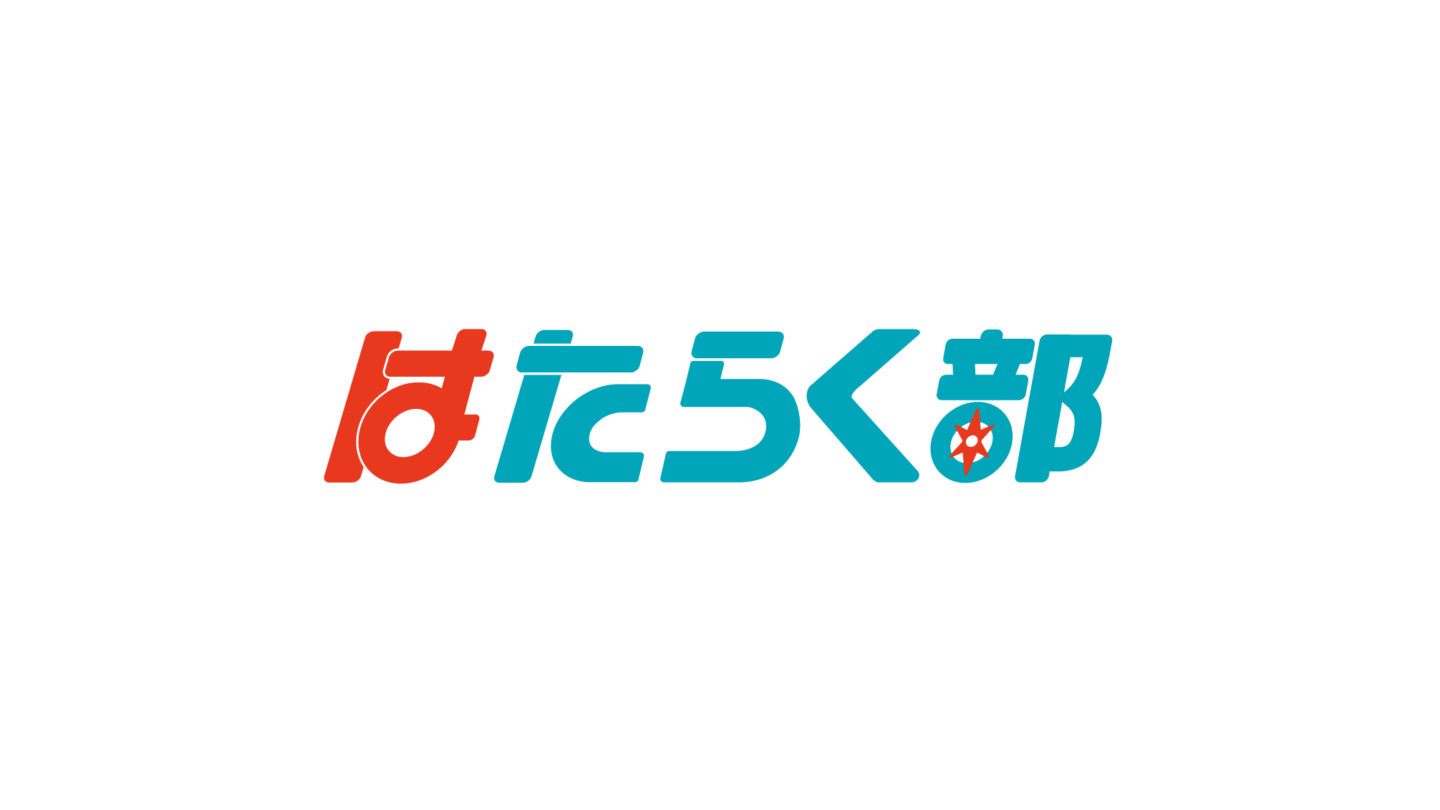
自己推薦書に書くことがない?経験が少ないと悩む学生のための完全ガイド

総合型選抜で受験を考えている皆さん、こんな悩みを持っていませんか?
- 「自己推薦書に書く事が無い」
- 「これといった実績や課外活動を行っていない」
- 「部活は頑張ってきたけど他の人に比べるとエピソードが弱い」
上記のような悩みを持つ人は自己推薦書には特別な経験や賞暦が必要だと考えているのでは無いでしょうか。
この記事では、総合型選抜での入試を実際に経験した筆者による、あなただけの個性あふれる自己推薦書を書くための考え方を伝授していきます!
この記事を読み終わるころには、自己推薦書に書きたいことが沢山思いついている事でしょう!
どうして「書くことがない」と感じるのか?よくある2つの原因
では、なぜ自己推薦書に「書く事が無い」と感じるのでしょうか?
それは、自分の持っているエピソードに対する理解度が低く、周りと比較して自己推薦書に書くほどのエピソードではないと判断してしまっているからです。
他人と比較してしまう心理
総合型選抜を受験する学生の中には、大規模な課外活動の経験や、部活などの輝かしい賞暦を持っている人も多くいます。それを自分の持つ実績やエピソードと比較して、自分は自己推薦書に書ける程の大きな功績が無い、つまり「書く事が無い」という考えに至ってしまうのです。
自分の経験を過小評価してしまう落とし穴
自身が持つ実績やエピソードが大したことないと考えている人は、自分の持つ実績やエピソードの、その本当の価値をまだ理解できていないかもしれません。あなたが経験の中で感じたこと、考えたことは誰にもマネする事の出来ない宝物です!
そもそも自己推薦書とは?
自己推薦書とは、「なぜ自分はその大学への入学に適しているのか」を自身の経験、強みや長所などを交えて記載するものになります。
大学が自己推薦書の提出を求める理由は、自己推薦書を通してあなたの人間性(どんな人物なのか)を見るためです。
自己推薦書で求められる人間性とは、「大学が求める生徒像」とマッチしているかどうかということです。
高校生活でどんなことを経験し、その経験から何を学んだのかを振り返り、自分にしか書くことができない、個性あふれる自己推薦書を目指しましょう。
経験こそがあなたの武器
自己推薦書は以下の構成で書かれることが多いです。
- ①自身のアピールポイント(強み)
- ②アピールポイントを裏付ける、経験エピソード
- ③自身の強みを入学後どのように活かすのか
- ④入学にあたっての決意(大学生活で成し遂げたいことなど)
①で書く自身の強みは自分の得意なことを簡潔に表現する必要があるため、「責任感」や「課題解決能力」など、他の受験生と重複しやすい表現になります。
しかし②の経験エピソードこそが、本当にあなたの個性を際立たせるポイントです。
いつ・どこで・誰と何をしたかという具体的な場面設定と、そのとき抱いたリアルな感情、さらにそこから得た学びや行動の変化を丁寧に描くことで、他者と被らない「あなた自身の物語」を語ることができます。
※自己推薦書のより具体的な書き方や例文について詳しくはこちらの記事をチェックしてみてください!
経験が少なくても大丈夫!自分の“強み”を引き出す自己分析3ステップ
「経験が他者と差別化できる武器になる事は分かったけど、そもそも書ける経験が少ない…」と困っている学生の皆さん、自己推薦書における経験とは「インターンシップ」や「ボランティア」といった課外活動だけを指す訳ではありません。以下の3ステップを通して自分の経験を見直してみましょう!
STEP1 過去の出来事をとにかく書き出す
まずは「これまでに経験したあらゆる出来事」を箇条書きで洗い出します。
授業の発表、部活の練習、アルバイトの失敗、家族の手伝い、テスト勉強の工夫など、小さなことも含めて構いません。なぜなら、最初から「これは大したことない経験だ」と取捨選択してしまうと、思いがけない強みの種を見落とすからです。全体像を把握することで、自分でも気づかなかったユニークなエピソードや思わぬ繋がりを発掘できます。
STEP2 「続けたこと」「頑張ったこと」「悔しかったこと」に分類してみる
次に、STEP1で書き出した出来事を「続けたこと」「頑張ったこと」「悔しかったこと」の3つに振り分けます。
この分類作業は、自分がどの領域で粘り強さを発揮したのか、どんな場面で本気を出したのか、どこに強いモチベーションや課題意識があったのかを可視化するためです。自分の行動のパターンを見つけることで、考え方や大切にしていることがわかりやすくなり、エピソード選びがスムーズになります。
STEP3 書き出した出来事に「何を感じたか」をプラスする
最後に、STEP2で分類した各エピソードについて「そのときに自分は何を感じたのか」を付け加えます。
達成感、焦り、葛藤、喜びなど、リアルな感情を書き込むことで、単なる経験の羅列ではなく「自分だけの物語」に深みが生まれます。気持ちの動きを整理することで、読み手に共感を呼び起こす説得力ある自己推薦書が完成します。
平凡な経験を魅力的なエピソードに変えるコツ
日常のささやかな出来事も、伝え方次第で印象的なアピールになります。
自己推薦書では、文字だけで自分を伝える必要があるため、読み手に「なるほど」「確かに」と共感してもらえるかが重要です。視点を変えて、感じたことや行動の流れを丁寧に書くことで、読み手である試験官の共感を呼び起こしましょう。
成果や実績以外で評価されるポイント
自己推薦書では、単なる成果や数字だけでなく、「課題発見力」「継続力」「柔軟性」といったプロセスの要素も高く評価されます。「何を成し遂げたか」以上に、「どのように取り組んだか」「何を学んだか」という部分こそが他者との差別化ポイントであり、試験官が見ているポイントでもあります。
例:
×悪い例
「私は毎朝6時に5kmのジョギングを1年間続けました。」
──問題点:行動の事実だけを述べており、どう取り組んだかやそこから何を学んだかがまったく伝わりません。
○良い例
「入学当初は授業中の眠気に悩んでいたため、朝6時から5kmのジョギングを習慣化しました。寒さや疲労で挫けそうになるたびに、走り終えた後の爽快感と1日の集中力向上を思い出し、自分に声をかけながら継続。振り返りノートに体調やペースの変化を記録することで、自己管理力と目標設定の重要性を実感しました。」
──ポイント:なぜ始めたか、続けるためにどう自分を支えたか、そして振り返りを通じて何を学んだかを具体的に示しています。
挑戦した過程や努力をストーリー化する
試験官は文面でしかあなたの経験を知る事が出来ません。いかにリアルに自身の経験を語れるかがカギになってきます。
経験をストーリーとして描く際は、起承転結の流れを意識しましょう。
- (起)まず「挑戦の背景」を明示する。
- (承)次に「具体的な行動」を描写する。
- (転)その後「思わぬ壁や葛藤」を挿入する。
- (結)最後に「課題を乗り越えた結果と学び」で締める。
特にあなたがぶつかった壁や問題、そしてあなたがどのようにして乗り越えたのかを語ることで、試験官にあなたの成長ストーリーをリアルに伝える事が出来ます。
例:
(起) 授業中に眠気を感じるほど運動不足を実感し、集中力向上のため朝のジョギングを決意しました。
(承) 毎朝6時に5kmを走り、走行後はペースや体調をノートに記録しつつ継続しました。
(転)真冬の寒さや期末試験前の疲労で何度も挫けそうになり、「今日は休もうか」と葛藤しました。
(結)それでも走り切った爽快感が糧となり、授業中の集中力が格段に上がり、PDCAサイクルの重要性を自覚しました。
何をしたかより何を感じたかを伝える
自己推薦書を書く上で陥りがちなミスは「行動の羅列」です。ただ自分が何を行ってきたかを書くだけではプロフィールになってしまいます。そうならないためには、自分がその瞬間に抱いた感情を丁寧に描くことがポイントです。自分の心の動きや気づきを具体的に示すことで、読み手はあなたの人間性や成長の深さを感じ取りやすくなります。
例:
× 悪い例
「 私は、毎朝6時から5kmのジョギングを1年間続けました。雨の日も風の日も休まず走り切り、集中力が向上しました。」
──問題点:何をしたかしか書かれておらず、どんな感情の揺れや気づきがあったのかが伝わりません。
○ 良い例
「朝6時、最初の一歩を踏み出したときは『本当に続けられるだろうか』という不安に胸が締めつけられました。3km地点で足が重くなった瞬間には『ここで諦めたら自分に負ける』という悔しさが込み上げ、深呼吸をしてペースを取り戻しました。ゴール後に得た爽快感は、単なる体力向上以上に『自分ならやり抜ける』という自信へとつながりました。」
──ポイント:行動に加え、その瞬間に抱いた不安・悔しさ・達成感を具体的に描写し、読み手にあなたの成長の実感を伝えています。
具体的な自己推薦書の構成と例
ここまで日々のエピソードを個性的な自己推薦書に落とし込む方法を紹介してきましたが、実際に日常のエピソードを元に書いた自己推薦書を見て考え方の参考にしてください!
【テーマ】毎朝のジョギングを継続した事
高校入学当初、運動不足で集中力が続かず、授業中に眠気を感じることが増えていました。そこで私は「朝のジョギング」を習慣化することを決意しました。雨の日も試験前日も、毎朝6時に5km走ることを1年間一度も途切れさせずに続けました。最初の100mでは「本当に続けられるだろうか」という不安で足取りが重くなり、3km地点では「ここで休んだほうが楽だ」という葛藤に襲われました。しかし、その悔しさをバネに呼吸を整え直し、もう一度ペースを維持。走り終えた瞬間に得られる爽快感が毎日の原動力となり、やり抜く力を実感できました。この経験を通じて、私は「継続力」だけでなく、目標設定→計画→実行→振り返りというPDCAサイクルを身につけました。貴学では、PBL形式のグループワークや研究活動において、この自己管理能力を活かし、困難に直面しても最後まで粘り強く課題に取り組み、チームを支える人材を目指します。1年間のジョギングが、私の学びの基盤となっています。
今すぐやってみよう!自己推薦書を書くための第一歩
今すぐ始められる自己推薦書作成の第一歩は、自分の経験と向き合うこと。まずは思い出せる限りの出来事を時系列で書き出してみましょう。一番下にお手本があるので是非参考にしてみてください!
紙とペンの用意は出来ましたか?それでは第一歩を踏み出しましょう!
「自分史グラフ」を作成する
まずは自分の人生を俯瞰するため、幼少期から現在までに経験したできごとを時系列でグラフ形式で書き起こします。学校行事、部活、アルバイト、家族との思い出など、大小問わず思い浮かぶ限り書き込みましょう。
はじめから取捨選択せずに書き出すことで、自分でも忘れていた経験や隠れたエピソードが浮かび上がり、自己推薦書のネタが豊富になります。

筆者の自分史の例
エピソードの深掘りシートをつくる
グラフで書き出したできごとから、特に印象深いものをピックアップし、以下の項目で深掘りシートを作成します。
- 状況(いつ・どこで・誰と)
- 課題や目標
- 自分の行動
- 感じたこと
- 学び・成長
このフォーマットを使うことで、平凡な出来事にも論理的な構造が生まれ、読みやすく説得力のある文章が書けるようになります。
「小さな成功」「挫折」「困難」をピックアップする
すべての経験が自己推薦書に適しているわけではありません。
そこで、リストの中から「小さな成功」「挫折」「困難」をそれぞれ3〜5つずつ選び出しましょう。成功体験は自信とモチベーション、挫折や困難は課題発見力や粘り強さを示す材料になります。バランスよく盛り込むことで、多面的な人間性をアピールできます。
第三者に「自分の強み・弱み」を聞いてみる
自分では気づきにくい強み・弱みを把握するため、家族・友人・先生など出来るだけあなたの事をよく知っている第三者にインタビューしましょう。
「自分のどんなところを評価しているか」「どんな場面で頼りになったか」など具体的に尋ねることで、自分史リストや深掘りシートに新たな視点が加わります。他者の視点を取り入れることで、自己推薦書に客観性と説得力が生まれます。
まとめ:自信をもって自己推薦書を書き始めよう!
ここまで日常の小さな出来事をあなたらしい武器に変えるヒントをお伝えしました。
大切なのは、ここで紹介したステップをベースに、自分自身の言葉でエピソードを紡ぎ出すことです。
「これなら書けそうだ」と感じた方法から一つずつ試してみてください。自分史リストを広げ、深掘りシートで視点を磨き、他者の声を取り入れる──このガイドに沿って行動すれば、必ず書くべきネタが見えてきます。
もし自分自身でイチから始めるのは難しそうだと感じた方は総合型選抜・AO入試対策歴15年の大ベテラン講師による無料進路相談でお気軽にご相談ください!大学のその先まで見据えて「あなたがこの先どうすべきか」を明確にお伝えいたします!
受験生の皆さん、あなたの経験は唯一無二。他者と比較することなく自信を持って、自己推薦書に取り組んでください。あなたの熱意と個性が詰まった文章が、合格へ繋がることを心から願っています。

足立陽菜
目標が無くなんとなく過ごした高校三年間。それでもはたらく部総合型選抜コースに出会い、真剣に自分の過去・未来に向き合った結果多くの気づきがありました。今は自身のパワーアップのためにはたらく部でのインターン活動のほかに大学での活動にも積極的に取り組んでいる真っ最中!